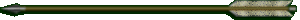|
むかしむかし、一人の風変わりな画家がいた。
彼は普通の人が見たら、何を描いたものだかわからない絵ばかり描いていた。でもムールに一度でも乗ったことがある人や、高い場所に登ったことのある人ならわかるはずだ。空から見下ろした海の細かい波しぶきと微妙に描き分けられた潮の色、黒く白く描かれたムールをはじめとした海鳥の影。あるいは地上からでは到底全貌をつかめない岬の姿。彼のアトリエは空、もっと正確に言えば彼の愛鳥の背の上だった。天気のいい日はキャンパスと絵の具をかかえて空を舞った。天気の悪い日は禽舎でムールの絵ばかり描いていた。
普通の者は基本的にムールを飼えない。けれど彼はムール調教師の息子で、けれど調教や武術を習得するよりもムールに乗って家出をし、そこで絵ばかり描いているような少年だったものだから、愛鳥一羽だけを手土産に親から勘当を受けてしまったんだ。それでも彼はこれ幸いとばかりに家を飛び出し、売れない風変わりな絵描きになったというわけさ。
あるとき、町で絵を売っていた画家のところに、ひとりの軍人が客として来た。ムールの一大生産地であるその町に、老いた愛鳥の替え馬ならぬ替え鳥を飼いに来たんだな。そんな職業だったものだから、画家の絵を見て、一目で上空からの絵と見抜いてしまった。
「これはどこから描いたんだね」
「海の上からです。ちょうど、あのあたりで。ほら、ここに描いてあるのがこの街ですわ」
軍人の問いに画家は海を指差し、次に絵を差して説明した。軍人は感心してその絵を買い、画家のムールを見せてくれとせがんだ。画家は自慢の愛鳥を見てもらえると大喜びで承諾し、軍人にムールを見せた。
画家のムールはけちのつけどころがないほど美しかった。画家が毎日欠かさずきれいに手入れをしてやり、自分が食べるものも惜しんでいい餌をやっていたからな。白黒まだらの羽毛はつやつや光り、胸は厚く、翼は大きく力強かった。くるくるよく動く瞳は宝石よりも美しく光る。いたずらっぽくも優しい瞳に軍人はすっかり魅せられてしまった。
「これはいいムールだ。どうだね、私にゆずらないかね。代価に糸目はつけないよ」
むろん画家は断った。軍人は何度も何度も繰り返し頼み込んだが、画家は決して首を縦に振らない。軍人は腹を立ててその日は宿に帰った。軍人は軍に二十日間の休みをもらってこの画家の町へ来ていたんだが、そのぎりぎりまで画家の家に毎日通って頼み込んだ。それでも画家は断り続けた。
最後の日、軍人はとうとう堪忍袋の緒を切らした。
「軍に逆らうとは、覚えておくがいい。必ずそのムールをわたしのものにして見せるからな」
ムール騎兵は総じて位が高い。ムールを飼うことができる者も、御すことができる者も限られているからな。この軍人も例に漏れず位が高く、金も権力も持っていた。
軍人は群の本拠地に戻るなり部下に命じ、不敬罪をでっちあげて画家の財産をとりあげてしまった。その中にはむろん、あのムールも含まれていたんだ。
画家はむろん抵抗した。売ってくれと頼まれ、それを断っただけなのに不敬罪に問われるなんざ、ばかな話だ。ムールに乗って逃げ回り、けれど軍のムール部隊に画家がどうして立ち向かえるだろう。威嚇のため武器を持ち出したムール騎兵に愛鳥が傷つけられることをおそれ、画家はとうとう降参した。連れてゆかれるムールの腹を見つめ、画家は地に額を打ちつけ泣きに泣いた。
この様子を聞いた軍人は、さすがにばつが悪くなった。連れてこられたあのムールも飼い主が突然変わったことに驚いたのか体を壊してしまった。あの美しかった羽毛は抜け落ち、くるくるしたよく輝く瞳はおどおど怯える悲しげな目つきに変わっていた。
「このムールの美しさを取り戻すためには、あの絵描きの手が必要だ。なんでも、あの絵描きはさるムール調教師の息子だというじゃないか。わたし専属のムール世話係として招こう」
部下はすぐさま画家の家に向かった。
ドアに鍵はかかっていなかった。何度ノックしても返事がなく、部下はのぞきこむだけならいいだろうとドアを開けたんだ。
薄暗い家の中は絵の具の香りに満ち満ちていた。真っ黒になったパレットが窓際に転がっている。そしてその隣にはキャンパス、キャンパス、キャンパス。青、赤、緑、黄色、考え付く限りの色で描かれた極彩色のムールの頭が、翼が、鉤爪が。
部下は部屋を見回した。極彩色のムールに覆われた部屋の中――伝令の目は一枚の絵に留まった。極彩色の中、ただ一枚のモノクローム。よくよく見てみればそれはただのモノクロではなく、ありったけの色の絵の具をまぜあわせて作られた、深い深い黒だった。
この画家には珍しい、あまりに珍しい人物画。ドクロを持ち、うつむいた男。いや、女。中性的な顔立ちの女神の背後には白い、あまりに白いムールの腹が大写しに。
そして画家は、その前に……。
*
――翼がありながら逃れられなかったわたしのムールよ――
これが画家の最期の言葉と言われている。誰が聴いたのかはわからない。伝令が家の中に入ったときかろうじて息があったのか、それとも何かに書きつけられていたのか。もしかすると後の人の空想の産物かもしれない。だが、この言葉は、全てから逃れる力を持ちながら、そこにとどまり死の神としての役を果たす風神と重ねられている。
外界へ向けられるはずの憎しみを、自らに押しこめたその悲しみ……この絵は後に「憎しみの風神」と名づけられ、王都の大神殿に奉納されて、その数年前、別の画家が描いた「喜びの風神」とともに飾られているんだ。
|