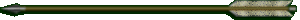さて、前に
「三日月の決闘」の話をしたな? クレーセ亡き後、謎のイッペルス守護者が現れクマ守護者ワグマと戦い、これを退けた。謎のイッペルスはその後、姿をくらまし、新しい守護者が別に決まった。これがエレーン、この話の主人公だ。
守護者は動物の種類によって決まり方が違う。サルのように前守護者の一番上の子供が守護者になる場合もあれば、キツネのように生まれたとき守護者が決まる生き物もいる。キツネはみんな赤茶色の体をしているが、守護者として生まれてきたキツネは銀色の毛並みをしているんだ。
オオカミやイッペルスの場合はその森最強のもの、群れのリーダーが守護者となる。こう一言で書いてしまえば違いなく見えるんだがな、オオカミとイッペルスもまた違うんだぞ。
オオカミはリーダーを畏れ敬い、守護者が病気や怪我や老衰で弱るまでほかのオオカミは勝負を挑まない。だが、イッペルスは毎年、秋に、ふだんは森中でバラバラに散っている全てのイッペルスが集まって巨大な群れとなり、雄は雌をめぐって決闘する。この決闘こそが守護者争奪戦だ。守護者は毎年、挑戦者を十何頭も退けんとならん。
それともう一つ雄雌の差があってだな。オオカミにはさして差はない。たしかに雄が守護者になることが多いんだが、雌の守護者も珍しくないな。だが、イッペルスは必ず雄だ。そもそもからして角つきあわせて戦わんとならんからな、雌は守護者になりようがないというわけだ。
ところが、前守護者が守護者争奪戦でない別の場、不慮の事故やらなんやらで命を落とした場合は地神がじきじきに次期守護者をお選びになる。こういう場合も大抵雄が選ばれてきたんだが……どういうわけかクレーセ亡き後、地神は雌のエレーンをお選びになったんだ。雌が守護者になったことはそれまで一度もなかった。エレーンの後にもいない。エレーンは唯一の雌イッペルス守護者なんだよ。
もちろん選ばれたエレーンは困り果てた。雌であるどころか、人間の歳にあてはめてみれば十四、五歳の少女でしかなかったからな。それでも責任感は一人前、ほっそりした足で森を端から端まで駆け回り、聖域を守り、マナーの悪い狩人を叱り、あらゆる生き物の出産の手助けをし、森を守った。周りももちろん度肝を抜かれたが、エレーンの働きぶりを見て、さすが地神の選択には間違いがないとほめたたえた。
秋には守護者争奪戦がある。どうなることかと周りは固唾を呑んだが、雄たちは誰もエレーンに向かっていこうとしなかった。さすがに気がとがめたんだろう。エレーンは寿命が尽きるまで守護者の任を果たすことを約束されたようだった。
そうして月日がたっていった。人に化けたとき少女の姿をしていたエレーンはすっかり大人びて、美しい女性に化けるようになっていった。ところがこれが年頃の狩人には眩しすぎたらしくてな。しかも場所が場所、人気のない森のど真ん中だ。地神の裁きも恐れぬ輩がわざと聖域に近づき、エレーンを呼び寄せて狼藉をはたらこうとする事件が次から次へと起こった。むろんエレーンも黙っていないさ。すぐさまイッペルスの姿に戻って蹄でしこたま蹴りつけた。
雌でもイッペルスはイッペルス、人間の力じゃとてもじゃないがかないはしない。それでもエレーンは精神的にかなり参ってしまっていた。行きたくないと思ってもエレーンは守護者だ。聖域に人間が近づけばどうあろうと飛んでいって止めなきゃならん。
そんなある日のことだった。人間が聖域に近づく気配を感じて止めに向かったエレーンは、またも下卑た笑みを浮かべた見習い猟師三人と向かい合うはめになった。最初からわかっていたからエレーンは人に化けず、イッペルスの姿で行ったんだが、やつらもやつらでな。イッペルス用の罠を張って待ち構えていたんだよ。イッペルスしかかからないような高さに糸を張ってな、イッペルスがそこを通って糸を切ると上から網が落ちてくるしかけだ。
エレーンは罠にかかってしまった。いくらなんでも森の守護者にこんなことはしまいと思っていたのさ。守護者は厳格で有名な地神の僕だ。神を畏れぬにもほどがある。が、あれよあれよという間にエレーンは両前足、後ろ両足をそれぞれしばられ、まったく身動きできない姿にされてしまった。
人の姿になって自分たちのなぐさみものになれ、さもなくば聖域に足を踏み入れると男どもはエレーンを脅す。エレーンも誇り高きイッペルスだ、辱めを受けるなら迷わず自死を選ぶところだが、エレーンは守護者でもある。守護者の至上命令は絶対に人間を聖域に入れぬこと。エレーンは怒りと絶望の叫びをあげた。
と、絶体絶命のそのときだ。
「てめェら何をしとるか! 動くなァ!」
怒声のあがった方を見てみれば、エレーンもよく知っている老猟師が使いこんだ弓をかまえ、エレーンを取り囲む男の一人にぴたりと鏃を向けている。
男らは緊張したが、相手が爺さんひとりとわかると肩の力を抜いた。
「おいおい爺さん、なんだよ一人でどうしようっていうんだ?」
からかう口調で言った男の腕を一瞬にして矢がつらぬいた。
「たしかに爺さんだがァ、四十余年も猟をやってきた男ォなめるんでねェぞ。守護者さまから離れろォ!」
焦った男らも自分たちの弓に矢をつがえたが、爺さんまでの距離がかなりある。それぞれ矢を放ったが、見習い猟師の腕では到底当たらない。かなわぬと悟った男らはエレーンの後ろに身を伏せた。イッペルスの巨体を楯にしたわけだ。
エレーンはその隙を見逃さなかった。足を全部縛られた状態だが、それでも転がることはできる。もろにイッペルスの巨体の下敷きになり、骨を砕かれた男らは悲鳴をあげた。泣き叫びつつ逃げるんだが、エレーンの怒りは相当のものだ。駆けつけた爺さんに足を自由にしてもらったエレーンは男らに追いすがり、こてんぱんに叩きのめした。一人は両足を蹴り砕かれ、もう一人は腕を踏み砕かれた上に脊髄に傷を負って半身不随になった。最後の一人は肋骨を二本砕かれ、さらに視力も失った。
返り血をさんざん浴びたエレーンは最後に三人をにらみつけ、いつの間にか近づいてきていた爺さんを振り返った。
「自業自得とはいえ、こうまでされると気の毒ですなァ。お怪我はなかですかァ? はよう川かどこかへ行って洗い流した方がよろしい、オオカミどもが寄ってきますぜェ」
エレーンは黙って老猟師を見つめていた。エレーンは人間嫌いになりかかっていたから、本当はとっとと逃げ出してしまいたかったんだ。だが、どういうわけやらそのまま立ち去りたくない気持ちにもなっていた。エレーンはしばらくそのまま立ちつくし、そうだ人間はこういうときお礼を言うものなんだと思い当たった。そんな知識はあったんだが、実際にお礼を言うべき人間を前にするとどうしていいものやらわからなくなってしまったんだ。
エレーンは爺さんに近づいて頭を下げ、長い首を猟師の肩にもたれかけさせた。イッペルスは友達にこうするものなんだよ。そう互いの肩ごしに首を回して、首の付け根を軽くかんでマッサージしてやる。だが、人間である爺さんの肩の後ろはむろん空っぽだ。恥ずかしくなって耳をぱたぱたさせていると、爺さんは馬にするように軽くエレーンの首をなでた。
「震えておいでではないですかァ。えェ? もう少し早く駆けつければよかったんですがなァ。申し訳ないですなァ……」
エレーンは体をぶるりと一つゆすって人の姿になると、爺さんと向かい合って目を伏せた。
「ありがとう」
やっと思い出せた人間の感謝の言葉に爺さんは笑っていわく、
「若いもんどもは、美女の蹴りの一撃より感謝の言葉のほうがよっぽど嬉しいと知りませんからなァ。いやはや、こんなジジイにはもったいなかァ」
足元から瀕死の男どもの呪詛の声があがったが、エレーンの一睨みで消えうせた。エレーンはそれから次は目だけで感謝を爺さんに伝えると、またイッペルスの姿に戻って森の奥へと駆け去っていったんだ。
爺さんは結局、エレーンが去った後に三人の男の手当てをしてやり、「戻ってくるまでにオオカミどもォが来たら、運がなかったとあきらめろォ!」と言い置いて村へ戻ると、人を集めて三人を助けに来てやった。けれどやはりというべきか時すでに遅し、三人の転がっていた場所には血だまりと服の残骸以外はもはや残っていなかった。
爺さんはその一件以来、よく森の奥深くへ来るようになった。不届き者がいないか見回ってくれているらしい。エレーンは爺さんを見つけるとそっと近づき、木陰から見守った。こっそり見守るだけのつもりだったんだが、相手は熟練の猟師だ。すぐに気づかれてしまい出て行かざるをえなくなった。爺さんはあの若い見習いたちのその後を妙ななまりのある口調で語り、エレーンはそばによりそって話を聞いた。
数日後にも、さらにその数日後にも、エレーンは爺さんを見つけてそっと後を追い、また気づかれて、そばによりそい話をした。そんなことを何回か繰り返すにつれエレーンはだんだんとこの爺さんを慕うようになっていった。今日は来てくれなかったとなればがっかりし、リンゴをくれたといっては大喜びで跳ね回った。今までそんなことはなかったんだが爺さんの村へ出かけていってお茶をごちそうになることさえあった。
そうして楽しく暮らしていたんだが、爺さんも歳でな。目がだんだんかすむようになって猟ができなくなった。それまで貯めていた金で生活は困らなかったんだが、この爺さんは猟が生きがいだったんだな。とたんに弱っていった。胸を患ってしまったんだよ。
エレーンはもちろん心配した。それで森で木の実や薬草を集め、爺さんの見舞いへ行ったんだ。爺さんは止まらない咳に苦しげに顔をゆがめながら、それでもエレーンを歓迎した。咳の合間をぬっていつものように世間話をし、いつものようにエレーンを笑わせた。でもな、エレーンが帰る段になって爺さんは悲しげな顔をしてだな、こうぽつりとこぼしたんだよ。
「エレーン様ァ、ひとォつ、懺悔してもよろしいですかなァ……」
なんだろうとエレーンが爺さんを見返すと、爺さんはもじもじしながら言葉をついだ。
「エレーン様ァにはじめてお会いしたときィ、わし、聖域ィに入ろうとォ、しとったんじゃァ」
爺さんは咳をし、驚きに声も出ないエレーンに笑いかけた。
「その後もあのあたりをうろうろしておったのもォ、聖域ィに入ろうとォしとったからじゃァ。けんども、毎回エレーン様ァに見つかってしもうてのォ。がきィんころからァ、ずっとォ、入ってみたかったんじゃァ。死ぬ前にィ、一度でいい、入ってみたかったんじゃァ。けんども、エレーン様ァの悲しむ顔はァ、見たくのうてのォ」
エレーンは怒らず、ただ悲しみにうちひしがれて爺さんの家を後にした。善意でもって接してくれていると思っていた爺さんが、実はエレーンの隙をついて聖域に入ろうとしていたとは。けれど、エレーンを悲しませまいと今まで我慢してくれたのは事実、エレーンを裏切る気はなかったのは明らかだ。爺さんは本当に心からエレーンを思ってくれていた。
エレーンはまっすぐに聖域へ向かい、地神に爺さんの願いを叶えてくれるよう懇願した。あの爺さんなら聖域を荒らすようなことはしまいと。だが、地神の返答は「否」だった。エレーンは全身全霊をこめて地神に祈った。だが、もう地神の返答は返ってこなかった。
やがて祈り疲れてそのまま眠ってしまっていたエレーンは、聖域に人の近づく気配を感じて目を覚ました。エレーンはすぐさま飛んでいき、病んだ体をひきずり夜の森を歩く爺さんを見つけた。
まっすぐに爺さんは聖域へ向かっている。エレーンはなんとしてでも止めなければならない立場だ。けれど、ぜいぜい息をきらしながら、普段なら必ず気づく位置にいるエレーンにも気づかないまま奥へ奥へと進んでいく爺さん、親愛なる爺さんにエレーンはどうしても声をかけられなかったんだ。
エレーンは止めなかった。聖域へ先回りし、ぼろぼろ泣きながらそこで爺さんを待ち構えた。やがて現れた爺さんはエレーンと向かい合い、申し訳なさそうに笑った。エレーンは黙ったまま最後の一歩を踏み出すのを待ち、完全にそこへ足を踏み入れた爺さんを抱きしめた。
「申し訳ねェ、エレーン様ァ。あなたの涙ァ、見とうなかったんじゃがァ。もう先のないわしじゃァ、地神様ァの裁きも、おそろしゅうないわい。夢だったんじゃァ……ずっとずっと、ここへ来るのが夢だったんじゃァ……」
エレーンはただただ黙って泣きながら爺さんを胸に抱いていた。地神により裁きが下れば、それを実行するのは森の守護者であるエレーンの役目だ。最悪爺さんに手をかけなければならなくなる。むろん人を聖域に入れてしまったエレーンも罰されるはずだった。
エレーンは抱擁をとくと爺さんにゆっくり背を向け、聖域の中心部に向かって歩いていった。爺さんは聖域にしか咲かない黄金の花チュユルの花弁をそっとなで、そこに満ち満ちる生気を胸いっぱいに吸いこみ、それ以上は何もせず聖域を後にした。
森を無理をして歩いたせいか、翌日から爺さんの様態はいよいよ悪化した。エレーンに詫びに行くどころか咳が昼も夜もまったく止まらなくなり、身の回りのこともできずベッドに寝たきりになってしまった。
だが四日後の夜、ふぅっと急に体のだるさが取れた。ずっと爺さんを苦しめていた咳もぴたりと止まっていた。
爺さんは起きあがり、森をのぞんだ。森が爺さんを呼んでいた。
爺さんは家にあるなかで一番新しくて立派な狩人の服をまとって使いこんだ弓矢を背負い、地神の裁きを受けるべく森へ入っていったんだ。
行方不明になった爺さんの仲間、狩人連中は、もう余命がないと悟った爺さんは森へ分け入りその体を自らオオカミやクマに与えたものだと思っていた。
ところが猟期になって森のなかの猟師小屋へ行ってみれば、爺さんが、しかも病のかけらもない元気な爺さんが、そばに座ったエレーンと談笑しながら小屋で燃料にする薪を割っているじゃないか。仰天した猟師は爺さんと話す余裕もなく村へとんで帰って、他の猟師をみんなごっそり連れてきた。
爺さんは笑い、かつてエレーンを守った褒美として地神に病を治してもらった、その代償としてエレーンをずっと守り続けることを誓ったのだと説明した。猟師たちはまだ幽霊じゃないかと半信半疑だったんだが、エレーンがにこにこしながら肯定するので、やっと信じて、再会を泣きながら喜んだ。
だが、爺さんが語ったのは事実なんだが、地神の裁きの一面に過ぎなかった。地神はもうあと数日しか余命のない爺さんへの罰が命だけでは足りないと思われる一方で、エレーンの嘆願と爺さんのかつての功を考慮なされたんだな。
爺さんはエレーンと共に森を守る、いわば人間の守護者になった。爺さんの命はエレーンの余命を削ることで保たれた。爺さんはエレーンの命が続く限り生き続けられる、けれどな、エレーンの命を削っているのだという事実はずっと爺さんを苦しめた。爺さんに命を吸い取られることがエレーンに科せられた罰だった。エレーンはイッペルスとしては長く生きたが、人間並みの長い時を生きる守護者としては短命だった。
それでも爺さんをおのが手にかけなくていいとなった、しかも爺さんが死ななくていいとわかったエレーンが手放しで喜んだのは言うまでもない。
なにはともあれ二人は力をあわせ、命尽きるまで森を守ったんだとさ。